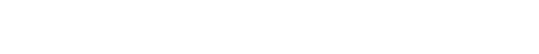『森が呼んでいる (後編)』

森に入ると、虫は脚や頭髪をめがけて襲ってくるし、顔は蜘蛛の巣だらけになるし、野生のヘラジカなんか見かけた日には心臓が飛び出そうになるし、でもひとたび足を踏み入れると途端に心はクリアになり、空気は澄んで肌に優しく馴染み、目に飛び込んでくる不思議な植物や動物が地球と自然と生命の神秘と奇跡と荘厳さをわたしたちに語りかけてくれるような気になれる。抱えている心配事や不安はちっちゃなもので、生きてて良かったとひたすら思えてくるから不思議なものだ。
わたしが初めてフィンランドの森に初めて行ったのは2002年の秋。でもフィンランドの森の神秘さと魅力に目覚めたのは2009年のクリスマスだった。
父の親友で詩人のカイ・ニエミエン氏と、彼の生涯の伴侶であった陶芸家の故・エリナ・ソライネン氏の邸宅はポルヴォーから車で30分くらいのところにある。そこに数日宿泊させていただいていたクリスマスの前日の朝、まだ薄暗い外を見つめながら寝ぼけまなこで朝ごはんをのそのそ頬張っていた時だった。
庭で採れたクロスグリのシロップをお湯で溶いたお茶をエリナさんが焼いた陶器のマグカップからすすり、カレリアパイを食べていると、窓の外にリスがやって来た。エリナさんたちが冬の間に食糧が手に入らなくなるリスや鳥を心配して置いておいた餌を食べに来たのだ。フィンランドでリスと隣り合わせになって一緒に朝ごはんを食べているという事実がなんだか嬉しかった。真っ白な雪が深く降り積もる、とても静かな朝だった。
この地では自然はもっと身近なところにあり、自然と共に季節を歩み、慎ましく暮らしているんだと思うと、その生活は豪華ホテルのビュッフェの朝ごはんや、有り余るほどの選択肢があって、何でも買って何でも食べられるコンビニの朝ごはんよりもよっぽど贅沢な朝ごはんのように感じられた。
今となると本当に奇跡のようなのだけど、わたしが森のそばの暮らしに魅力を感じたその村は、夫のベンヤミンの生まれ育った村の隣、車で5分くらいのところにある。まさか約10年後に、そこでベンヤミンと野草を摘んだり、きのこを採ったり、ベンヤミンのご両親と野菜を栽培したりしているなんて。人生は偶然と奇跡で満ちている。



ベンヤミンの実家の周りにある森は、春は何種類もの野草や、可愛くて美味しくて身体に良い花が、夏にはベリーが、そして秋はきのこが、それはそれはたわわに実っている。昨今のフィンランドのレストランや料理家界隈では、伝統的なフィンランド料理を再評価する流れが起こって久しいため、ベリーや野草を料理に使ったり、冬のために保存食を作ったりすることがトレンドになっている。


フィンランドをはじめとした北欧諸国のレストラン業界では10年ほど前から、日本や中南米などの調理方法や味付けをどんどん採り入れながらも、自分たちの土地で昔から獲ることができる魚や野菜を使って、それぞれの素材の良さを活かしながら美味しいものを作る流れに変わってきている。地産地消の新しい形。わたしたちも、野草や花、きのこなど身近に自生していて食べられるものや、自分たちの手で育てた野菜などを使った料理を紹介するプロジェクトを続けている。始めた頃こそ手探りだったけれど、半年ほど森と家の往復を繰り返していくにつれて植物にも少しずつ詳しくなり、特徴や名前、種類や効用や味・調理方法など、頭の中に辞書を蓄えられるようになってきた。東京の都会育ちのわたしでもここまで来れるとは。歳を重ねるにつれて、大事なことやものの分別が少しずつつけられるようになった気がするが、その中で最近目指しているのは余計な物を持たない・買わない暮らし。自分にとって必要はものはほんのわずかで、代わりにものや不必要な道具に頼らずに、森や自然の中で生活していく知識をどんどんつけていきたいと思っている。


森を歩いたり、野草を採って食べたりお茶にしてみたり、自然と暮らすということが趣味になってから、今までよりさらに環境保護や自然保護について考えるようになった。数年前の自分からは考えもつかないような様々な知識が増えた。ベンヤミンや、ベンヤミンのご両親、また世界中の多くの人と共有できて、一生尽きることなく追究できる、とても良い趣味だと思っている。

秋の森といえばきのこ狩り。きのこ狩りにおける大前提は、きのこスポットを知ること。フィンランドの人々にとって、きのこが生える場所は毎年決まっているというのは常識なので、まずはきのこが生えている場所を把握するのが大事(そして大抵それは秘密となっていて滅多なことでは口外しない)。慣れてくるとだんだん、その森の木の種類、太陽の光の当たり方、土の種類、全体的な湿り気具合でどんなきのこがどこら辺に生えているか見当がついてくる。きのこを採っている時は、きっとこの森のこのスポットで来年もまたその来年もずっとここで採り続けるのだなと思うし、わたしが死んだあともきのこはこの場所に生え続けて次世代のお腹を膨らませ続けるのだと気づくと森の偉大さと時の壮大さに畏怖の念を覚える。わたしが来るずっと前から、この森はベンヤミンの家族の先祖たちに夢と食糧を与え続けてきたのだ。なんて素晴らしい存在なのだろう。

自生するきのこの殆どは、熱して食べる必要がある。調理して食べないとお腹を壊してしまうけれど、調理をすれば美味しく食べられるきのこは森にたくさんある。わたしたちは日頃、あまり意識をせずに火を起こし、食べ物や住処を熱したりして火を道具として利用しているが、火を使って料理すること、それこそが人間が動物と根本的に種を異にするを結果をもらたしたのだと主張する霊長類学者も多い。動物は火を道具として使わないし、動物は調理しない。動物は生のままものを食べる。しかし、例えば人間がチンパンジーと同じものを食べようとしても、人間は長期的には生存できないらしい。というのは、人間は生物学的に、すでに「調理したものを食べる」ように進化した生物なのだそうだ。ゴリラと人間の身体を比べると、身長はさほど変わらないのだが、歯や顎の骨、顎の筋肉や肋骨などは人間の方が圧倒的に小さく、代わりに脳は肥大化している。脳はカロリーを非常に食う「貪欲な」臓器で、人間はカロリーを大量に、できるだけ効率的に採る必要がある。そのためには消化にかける時間や労力をできるだけ削る必要がある。狩猟などによって得た肉を、死ぬ確率を低めつつ、かつ効率的に摂取するには火を使って調理をするほかなかったのだ。

ジャーナリストでハーヴァード大学の教授のマイケル・ポッランによれば、古代から人間は火を起こすことで神に煙を送り、動物と神の中間としての存在を示してきたという。火を使うことは大切な儀礼で、現代では料理は女性の仕事、または位の低い者の仕事というイメージがついて回るが、例えばホメロスの『オデュッセイア』では、ギリシャ神話の英雄たちが狩りをし、火を使い調理する様子が多く描かれている。英雄たちにとっては料理という行為は特権的な意味合いがあったのだ。
料理はわたしのライフワークだし、わたしの料理には哲学や愛、人生を通して見つけた視点などをどんどん込めていきたいと思っている。そして愛、自分を愛することや自然を愛すること、そしてそばにいる人を愛すること、それらは全て、森の中で自分の中の声をチューニングすることで生まれたり、優しく包み込むことができたり、自分の中に定まったりする。
森は育む。それは植物や動物、酸素や土だけじゃない。わたしたちの心のひだ、ひとつひとつに優しい声を届けてくれる。そして厳しい一面があるのも森。どの自然も、知識を持って挑むのとそうでないのでは全く違う様相を見せる。だからこそわたしは、森について、できるだけ多くのことを知りたいと思っている。

(この文章は2018年にnoteに書いたものを加筆・修正したものです。)
写真・文 : 吉田 みのり
KEYWORD
- #便利なアイテム
- #遊び心いっぱい
- #映える
- #ほっこりかわいい
- #こだわりの肌触り
- #おやすみ、世界。
- #日本初上陸
- #暮らしを豊かに
- #持ち歩きたくなる
- #ハンドメイド
- #天然素材
- #便利な道具
- #料理も上達
- #北欧 フィンランドからの手紙
- #セレブ愛用
- #アウトドアを楽しくする
- #アートのある暮らし
- #ココロ
- #オーガニック
- #自宅で洗える
- #家事も楽しく
- #My Likes My Lifestyle
- #おうち時間
- #おしゃれで便利
- #心地いい
- #北欧のおやつとごはん
- #時短
- #夏にぴったり
- #使い方いろいろ
- #おうち時間 暮らしを豊かに
- #サスティナブル
- #自分メンテナンス
- #長く愛せる
- #便利な道具、
- #テレワーク
- #北欧デザイン
- #私らしい
- #スウェーデン ABCブック
- #人間関係
- #ハイセンス
- #楽してキレイ
- #メンタルケア
- #トラベル
- #お悩み解消
- #withコロナ
- #リフレッシュ
- #お仕事
- #日々を 紡ぐ
- #明日輝く
- #ぬくもり
- #ライフスタイル
- #気分が上がる
- #いぬも、ねこも。
- #北欧インテリア
- #喜ばれる
- #人生・価値観